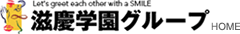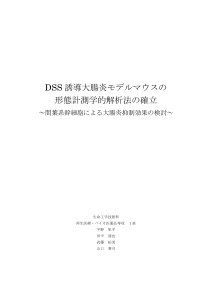抄録
I. 背景
炎症性腸疾患(IBD)の一つである潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜に糜爛や潰瘍が生じ、腹痛、ときに下血を伴う下痢、体重減少などの症状を呈する慢性炎症疾患である。残念ながら、未だ原因不明で根治療法が確立しておらず、IBDで苦しんでいる患者にとっては根治療法の確立は急務である。内視鏡観察において、正常大腸では粘膜表面は滑らかで、上皮を透かして粘膜内の血管が観察できる (Fig. 1左)が、潰瘍性大腸炎となると粘膜上皮の剥離と細胞浸潤によってその形態は著しく変化し(Fig. 1右)、病理組織像では、粘膜上皮の消失とともに腸腺構造も全く認められなくなる。現在、潰瘍性大腸炎の病態の解析やその治療法研究のため、正常C57BL/6Nマウスにデキストラン硫酸ナトリウム(DSS)を投与して作製したDSS誘導大腸炎モデルが広く用いられている。DSSによる大腸炎発症には、遺伝背景と組織修復機構が深く関わっていると考えられる。
近年、このような難治性疾患に対し、再生医療技術を応用した間葉系幹細胞による治療法が提唱されている。間葉系幹細胞(MSC)は、自己複製能力及び多分化能を持った細胞で、組織障害部位、及び炎症部位に集積する特性があり、免疫抑制作用、及び抗炎症作用を持っていると考えられており、近年、再生医療領域においては、本細胞によるIBDの細胞治療の可能性が検討されている。採取元として脂肪組織及び骨髄が挙げられている。
骨髄由来MSC(bMSC)はヒトにおいては採取することが困難で回収率も悪く、免疫系細胞に分化することが多く維持管理が難しいとされている。それに対して、脂肪組織由来MSC(aMSC)は採取が容易で回収率も高く、多くの細胞に分化することが可能であるといわれている。本研究ではaMSCを用いて大腸炎抑制効果を検討しようと考え、aMSCの調製を試みてきたが、その生産性が安定せず、大腸炎モデルへの投与が困難であった。しかしながら、bMSCに関しては培養することに成功したので、これを用いて大腸炎抑制効果を検討した。
ところで、マウスにDSSを投与すると大腸炎が生じるが、大腸の障害は均一に生じるわけではなく、部位によって障害の現れ方や程度が異なっている。そのため、治療法などを検討する場合は、どこを観察するかによって判定が異なってしまい、正確に評価することが困難であった。そこで、本研究ではDSSで誘発した大腸炎モデルマウスに同系マウスのbMSCを投与する事で、bMSCに大腸炎の障害に対する治療効果があるのかどうかを、組織切片上での形態計測学的解析によって評価可能かどうかを検討することとした。